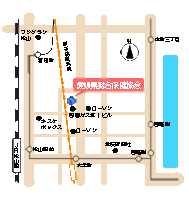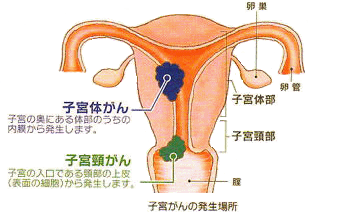|
|
 |
| |
TOP > 検査 > 病理細胞診検査 > 子宮がん検診について(検査)
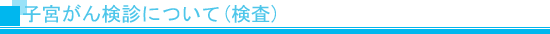
 |
子宮がんには“子宮頸がん”と“子宮体がん”があり、それぞれ発生する場所によって性質も形態も異なります。 |
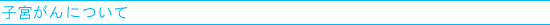
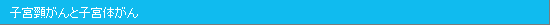
子宮は女性の生殖器で骨盤中央に位置し、膣に近い部分を頸部とよび、子宮の奥の赤ちゃんを育てる部分を体部と呼びます。子宮の入り口から1/3ほどの部分を頸部といい、奥の2/3部分を体部といいます。
この頸部から発生したがんが子宮頸がんであり、体部から発生したがんが子宮体がんです。日本では圧倒的に頸がんが多かったのですが、近年体がんの占める割合が増えてきています。その原因として、食事が欧米型に変わってきたことがあげられます。
両者は異なる性質をもっているため(好発年齢・発生原因・臨床症状・組織型・治療内容)区別して扱っています。
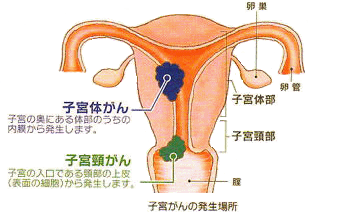 |
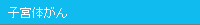
なりやすい人
50〜60歳代
閉経後の出血、月経異常あり
肥満、高血圧、糖尿病のある人
|
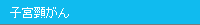
なりやすい人
30〜40歳代
20〜30歳代は増加(若年化)
性交渉多い、妊娠出産多い人
|
|
|
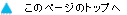 |
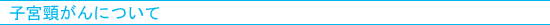
子宮がんにかかる人は、年間18,600人で、このうち子宮頸がんは約9,000人このうち2,700人が死亡しています。
しかし、子宮頸がん検診は多くのがん検診の中で最も効果の高い検診といわれています。対象部位が体表に近く細胞採取が容易で細胞診の信頼性が極めて高く、検診を継続的に受診することによってがんになる前段階である異形成という状態での発見が可能です。
また、近年ではHPVテストを組み入れた併用検診も行われるようになり、感度が一層向上しました。
平成23年度から一層の精度の向上を図るため、県下の子宮頸がん検診実施に際して、細胞採取法を液状化処理細胞診(LBC)法にて行い、結果を従来のクラス判定からベセスダシステムという報告様式に変更しました。
|
| 最近の傾向としては、 |
 |
受診者の固定化が著しく起こっている。これらの受診者の中で若年者からは、異形成といわれる状態で見つかりフォローが行われているが、がんが発見されるケースはまれである。
上記のことは、継続的に受診していれば頸部のがんになる前に発見されることが多いといえます。検診の実施に際しては、対象者の設定を効果的に行うことによって検診効果を高めることが可能と思われます。
|
 |
KCAといわれるヒトパピローマウィルスに感染したと思われる特徴的な異型細胞が、若年者を中心に多く見られるようになっています。
|
 |
子宮頸がん(頸部のがん)を対象に検診を行っているが、体部から剥離してきたがん細胞を認めることが以前に較べて多くなってきました。体がんの増加を頸がん検診を実施していても垣間見ることがあります。
|
 |
検診方法の多様化 従来から行われてきた検診車方式に加え、自治体によっては施設を利用して行われています。また、個人が検診の重要性を認識し医療機関にて受診する方もおられますが、検診対象者数に対する実施数は十分ではないといわれています。
当協会は検診車方式のほかにも、健康診断や人間ドックの際の検診項目として自施設でも行っています。
|
 |
最近の出来事として・・・・ 残念なことをひとつ! 受診者の方から、今年の検診はもう終わったんですか? 知らなかった・・・・ 事前に申込みが必要になったんですね・・・ そんな声をしばしば聞くことがありました。
情報の発信、啓発 PRが不足しているように思います。パンフの作成をはじめ担当者の方々との双方向通信を行っていきたいと思います。
|
|
|
|
どの検診にしても、事前の打合せに始まり、日程調整、検診の実施、結果の報告、要精検者の追跡と管理そして得られた情報の発信と啓発が不可欠です。自治体や関係協力機関そして地域の方々と協力し合い精度の高い検診を効率的に実施していきたいと考えています。 |
|
|
|
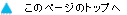
|
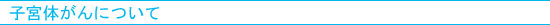
|
近年体がんが増加しており、子宮がんの約半数を占めるようになりました。子宮がんにかかる人は、年間18,600人で、このうち子宮体がんは約8,600人このうち2,000人が死亡しています。
検診は、不正出血があった人、とくに閉経後に不正出血があった人などを対象に実施することが望ましく、体がんの多くは腺がんです。リスクが高まる40歳後半からは、必要に応じて子宮頸がん検診といっしょに子宮体がんもチェックすることで早期発見が可能です。検査方法は、細い棒状のブラシを子宮内に挿入して子宮内膜細胞を採取し、顕微鏡で異常の有無を調べる細胞診、経膣超音波検査にて子宮内膜の状態に異常がないかを調べる検査などがあります。
|
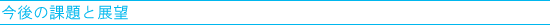
|
近年子宮頸がんの若年化が著しく進んでいます。このような状況の中、平成16年度から子宮がん検診の対象受診年齢が20歳以上に引き下げられました。
|
|
子宮頸がんは、HPV(Human Papilloma Virus)との関係が解明され、これまでの治療のための「早期発見」から、がんにならないための「がんの予防」へと意識を高めていくことが重要となってきます。愛媛県において子宮頸がん発生の原因とされる感染者の増加傾向が認められ、当協会実施の子宮がん検診においてもHPV感染の影響と考えられる異型細胞を発見する機会が多くなっています。
|
|
当施設は、これらの状況を発信・啓発するとともに、健診、検査に一層力を入れていきたいと考えています。
|
|
|
|
|
|
|
| |
![]() |
 |