|
|
||

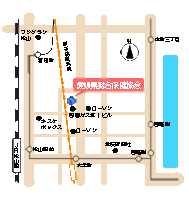
乳房X線撮影のことです。医師が触っただけでは見つからない、小さなしこりや石灰化を見つけます。 |
|
超音波により、乳がんを見つける方法です。医師が触っただけでは見つからない、小さなしこりを見つけます。乳腺の発達した方や若年者の方で、とくに威力を発揮します。 |
|
胸部X線検査は肺全体のX線撮影です。簡便で、浴びるX線量は少ないですが、病変が小さいと、見つけにくい場合があります。 |
|
CTスキャナーに横になり、X線を用いて、肺全体を輪切りにして、連続的に観察します。 |
|
X線で胃の中の粘膜を観察します。胃がんのほか、胃潰瘍やポリープも見つかることがあります。バリウムを飲むため、便秘がひどい方は検査に当たって注意が必要です。 |
|
ヘリコバクターピロリの長期にわたる持続感染が、慢性胃炎ひいては、がんを引き起こすきっかけになります。その感染の有無、胃炎の状態を調べ、リスクを判断します。がんそのものの有無を判定する検査ではないので、結果の取り扱いには注意が必要です。 |
大腸内にがんやポリープなどがあると、出血し、便に血が混じります。その血液を検出する検査です。 |
|
子宮頸部の細胞をブラシで採取し、細胞の形を顕微鏡で観察します。細胞は「ベセスダシステム」で分類します。前がん病変(がんの一歩前)で見つけることが可能です。 |
|
ウィルスの一種であるヒトパピローマウィルス(16型、18型)の長期にわたる持続感染が、がんを引き起こすきっかけとなります。 その感染の有無を調べ、リスクを判断します。 |
|
子宮体部の内膜より発生します。閉経後に多く報告されています。子宮内腔の形および内膜の厚さを経腟超音波装置を使用して測定し、異常の有無を判断します。 |
|
超音波により、腹部の臓器である肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、その他を対象に、異常の有無を検査します。 |
|
血液中のPSA(前立腺特異抗原)を測定し、その値で判定します。 |
当サイトに掲載されている全ての画像、文章等について、無断転用・無断転載することを禁じます。
